こんにちは。「普通の会社員の資産形成ラボ」管理人のパパとまるです。
今回は、会社員として自己成長を続けるために欠かせない「失敗との向き合い方」について考えてみたいと思います。
きっかけになったのは、マシュー・サイド著『失敗の科学』という一冊。
この本を読んで、「失敗」そのものに対する見方がガラリと変わりました。
そして、これからの時代、会社員こそ「失敗を活かす力」が重要になると確信しました。
この記事では、
- 失敗を恐れて動けない理由
- 組織が失敗から学ぶために必要な「仕組み」
- 若手指導で活かせるマインドセット
- そして私たちが今すぐできる「行動の変化」
について、具体的にまとめています。
1. なぜ私たちは失敗を恐れてしまうのか?
会社で新しいことに挑戦する時、「失敗したらどうしよう」とブレーキがかかる経験、ありませんか?
私自身もそうでした。
失敗することが恥ずかしい。
周囲の評価が怖い。
失敗=無能と思われるのが嫌だった。
『失敗の科学』では、人が失敗を恐れ、隠してしまう心理メカニズムについて詳しく解説されています。
たとえば「認知的不協和」。
これは、自分の信念や価値観と失敗の事実が矛盾したときに、人は無意識にその事実を否定し、自分を守ろうとするという心理です。
つまり、失敗を直視できないのは、「弱いから」ではなく、「人間として自然な反応」なのです。
2. 航空業界と医療業界に学ぶ、失敗から学ぶ組織と学べない組織の違い
本書では、失敗の扱い方の好例として、航空業界と医療業界が対比されています。
航空業界
- 事故が起きるとブラックボックスを回収
- データをもとに徹底的に原因分析
- 再発防止策が業界全体に迅速に共有
結果として、航空業界の事故率は劇的に改善しています。
医療業界
- ミスは「予測不能な偶発的事故」とされやすい
- 組織全体に学びが蓄積されにくい
- 「最善を尽くした」で終わる文化
この違いの本質は、「失敗に向き合う文化」と「仕組み」にあります。
個人の資質の問題ではなく、
仕組みがないから学びが生まれないのです。
3. 成長できる人と組織に共通するもの
失敗から学ぶには2つの要素が欠かせません。
- 成長型マインドセット
- 適切な仕組み
心理学者キャロル・ドゥエックの研究によれば、成長型マインドセットの持ち主は、「失敗は能力を伸ばす機会」と考え、粘り強く挑戦し続けます。
また、成長する組織には共通点があります。
それは「試行錯誤のプロセスを大事にしていること」。
うまくいかなくても、小さなトライ&エラーを繰り返し、そこからフィードバックを得て改善していく。
量をこなすことで質も向上していくのです。
4. 若手指導に活かせるヒント:失敗を「データ化」せよ
現場で若手指導をする立場にいる方も多いと思います。
私もそうですが、若手が失敗したとき、どう接するかに悩む場面が少なくありません。
失敗を責めるのではなく、「失敗をどうデータに変えるか」が大事です。
特に有効なのが「チェックリスト化」。
再発防止策をルール化するだけでなく、全員が共有できるフォーマットにすることで、チームのパフォーマンスが安定します。
また、「心理的安全性」がないと、失敗を隠そうとする心理が働きます。
普段から「ミスしても大丈夫、ただし改善しよう」という姿勢を伝えることで、成長型マインドセットを育てる環境を整えましょう。
5. 明日からできる行動とは?
私が本書から学んだ最大の気づきはこれです。
失敗は「避けるもの」ではなく、「活かすもの」
そのためには、
- 小さな失敗を恐れずに動く
- 失敗の記録と改善をセットで行う
- フィードバックを求めて行動する
というルーティンを日常に取り入れていきましょう。
失敗に真正面から向き合い、そこから学び、次に活かす——
それが、会社員としてのキャリア形成にも、副業にも、資産形成にも共通する「成長の鍵」だと私は思います。
📘紹介した書籍はこちら(アフィリエイトリンク)
『失敗の科学』マシュー・サイド著
👉 Amazonでチェックする
※リンクはAmazonアソシエイトを利用しています。
🎯まとめ:会社員こそ、失敗を「学び」に変える時代
私たち30〜40代の会社員にとって、
これからの時代に必要なのは「失敗しない力」ではなく、**「失敗から学ぶ力」**です。
自分の失敗も、若手の失敗も、
「改善の第一歩」として受け入れていける自分でありたいですね。
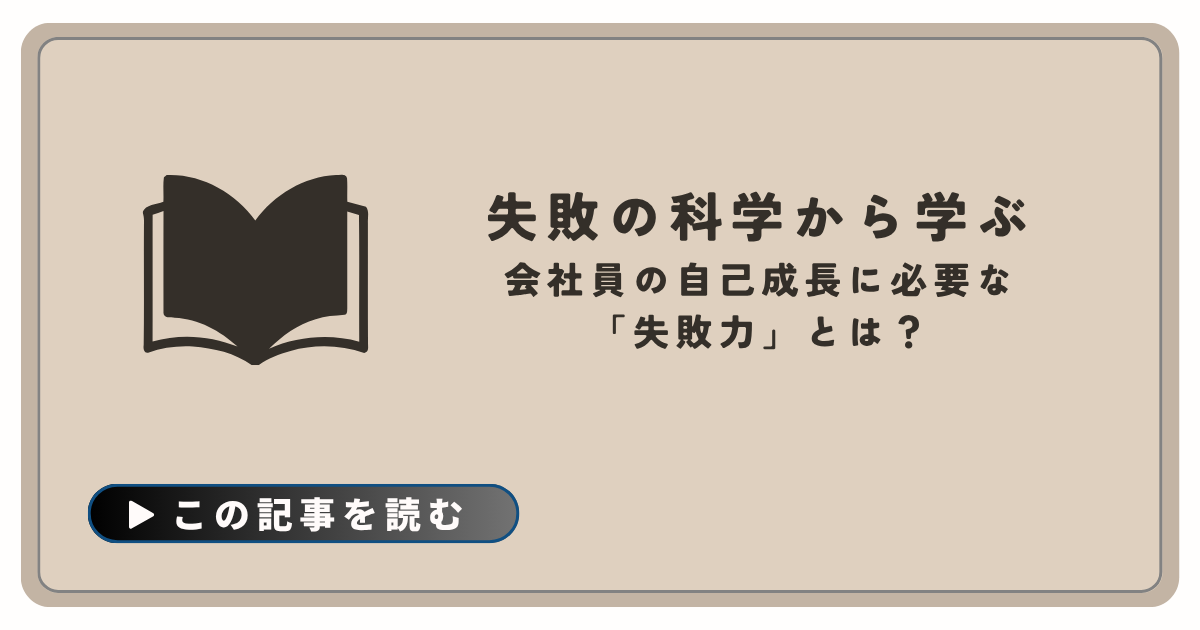
コメント